はじめに


こんにちは、ガゼルです。
レオパードゲッコーの飼育において、突然エサを食べなくなる「拒食」は珍しくない現象です。
飼っているレオパが餌を食べなくなってしまうと心配になりますよね。
レオパは長期間の絶食に耐える能力を持つ爬虫類ですが、拒食が長引くと健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
特に成長期にあるベビーやヤングのレオパにとって、十分な栄養摂取はとても重要なのです。
そのため、拒食が長く続く場合は原因を特定し、迅速に対処することが必要です。
拒食が考えられる主な原因としては、環境ストレス、体調不良、季節の変化などが挙げられます。
今回はレオパが拒食を起こしてしまう原因と効果的な対処法について考えてみたいと思います。
レオパードゲッコーの拒食の原因と対処法

拒食の原因
環境の変化(ストレス)
レオパードゲッコーは、丈夫そうに見えて意外と繊細な生き物です。
急激な環境の変化はレオパにとって大変なストレスになってしまいます。
特に、ショップやブリーダーさんからレオパをお迎えした後は一番ストレスがかかる場面です。
最初は可愛くて触りたくなりますが、気持ちを抑えて、環境に慣れるまでの数日間は外からそっと観察するようにしましょう。
また、飼育用具を取り換える時にも注意が必要です。
シェルターやヒーターは、レオパードゲッコーの生活に直接影響する大切な設備です。
これらを変更する時は、レオパのストレスを避けるため、急激な変更は控えましょう。

レオパにとって、人間に触られること(ハンドリング)は最大のストレス源となります。
特に餌を食べない拒食状態のときは、ハンドリングを避けることが重要です。
【レオパがストレスを感じやすいとき】
- お迎え時
- ケージレイアウトの変更
- 過度なハンドリング
餌の種類
レオパードゲッコーは、普段食べている餌を急に食べなくなることがあります。
このような場合は、いつも与えている餌を別の種類に変えてみるとあっさり解消されることがあります。
特に、人工フードを食べているレオパにこの傾向がよく見られ、餌を変えることで食欲を取り戻す助けになることがあります。

我が家のレオパの主なフードは「レオパゲル」です。
もしレオパゲルを食べなくなった場合は、次に「レオパブレンドフード」や「レオパドライ」を試します。
最近では、レオパのおやつとして「レプタイルピューレ」も選択肢に加えています。
これにより、レオパの食事のバリエーションが増え、食欲を引き出す手助けとなっています。

人工フードで飼育されている方は拒食になったときのために、保存期間の長いフードを数種類用意しておくと便利です!
また、昆虫で飼育されている方も昆虫の種類を変えてみたり、人工フードを試すのも効果があります。
「ハニーワーム」や「ミルワーム」などは、嗜好性が強いので拒食になっているレオパでも食べてくれる可能性が高いです。
ただし、これらの昆虫は栄養が偏ってしまうので与えるのは一時的なものにしましょう。
そして、ハニーワームなどに慣れてしまうと他の餌を食べなくなってしまう危険性もあります。
設定温度と湿度

レオパの飼育において、適切な温度管理はとても重要です。
ケージ内温度が20℃を下回ると、体内の代謝機能が低下し、その結果、餌を摂取しなくなってしまいます。
このため、飼育者は常に温度管理に注意を払う必要があります。
特に注意すべきは、ヒーター類のトラブルです。
機器の故障や停電などにより、飼育環境の温度が急激に低下する可能性があります。
このような事態を早期に発見し、対処するためには、毎日の温湿度チェックが欠かせません。
温湿度計を必ず設置し、定期的に確認することで、レオパの健康と快適な生活環境を維持することができます。
【温度と湿度の管理】
- 適正温度は25~30℃、湿度50~70%
- 床面にホットスポット作り温度勾配をつける
- 温湿度計の毎日欠かさずチェックする
温度と湿度の管理はレオパの飼育する上で一番重要なポイントです。
レオパの健康状態に密接に関係しているので、適切な道具を設置して快適に暮らせる環境を整えてあげましょう。
病気
上記の理由以外で拒食になっている場合、「腸閉塞」や「クリプト感染症」「マウスロット」などの病気にかかっていることも考えられます。
【病気が原因による拒食】
- 腸閉塞→餌の消化不良、床材の誤飲等
- クリプト感染症→寄生虫感染による食欲の低下
- マウスロット→口の周りが炎症を起こし、外的要因で餌を食べられない
レオパは便秘になってしまうと腸閉塞を引き起こす危険性があります。
「何日も排泄をしていない」「お腹がいつもより張っている」と感じたら便秘になっている可能性が高いです。
ケージの内側に霧吹きで水滴をつけることで、レオパは自然な方法で水分を摂取することができます。効果的な水分補給で排泄を促してあげましょう。

さらに、ケージ内にホットスポットを設置することも大切です。
ホットスポットとは、ケージ内の一部を他の場所よりも温かくした区域のことです。
この温かい場所は、レオパの消化器系の機能を促進し、特に腸の動きを活発にします。
これらの方法を組み合わせることで、レオパの水分補給と消化機能の両方をサポートし、健康状態を向上させることができます。
消化器系健康維持に、爬虫類専用整腸剤「レプラーゼ」が効果的です。
飲み水や餌に少量混ぜるだけで簡単に与えられ、レオパに自然な形で摂取させることができます。
定期的な使用で便秘の予防や解消が期待できますが、過度な使用は副作用を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
適切な使用量を守り、個体の状態に応じて調整することが大切です。

レオパは外見の変化から病気を察知できることがあるため、日々の観察は欠かせません。
例えば、クリプト感染症では体が急激に痩せ、特に尻尾が細くなります。
マウスロットでは口の周りが赤く腫れ、炎症や化膿が見られます。
これらの症状は、レオパの栄養摂取や全体的な健康に深刻な影響を与えます。
異常を発見したら、迅速に爬虫類専門の獣医師に相談することが重要です。
早期発見と適切な治療が、レオパの回復と健康維持の鍵となります。
日常的なケアと注意深い観察を心がけ、少しでも異変を感じたら躊躇せずに専門家に相談しましょう。

日々の細かい観察が病気の早期発見にもつながります!
拒食時の対処法
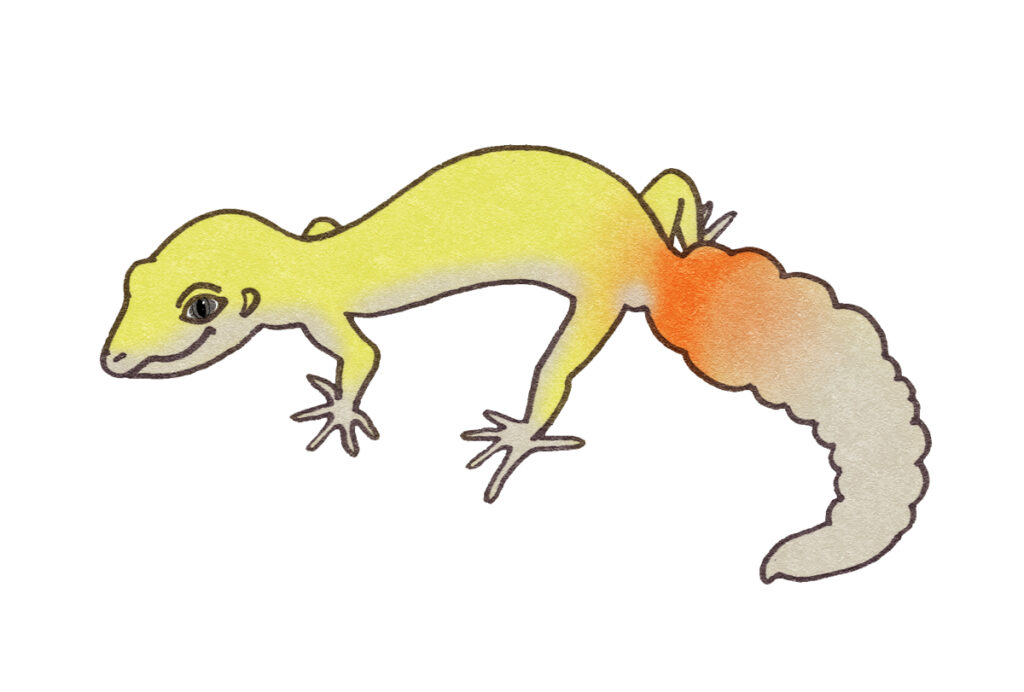
活き餌を与えてみる
レオパは本来、肉食性の爬虫類です。
野生では昆虫を捕食するため、飼育下でも活きた餌を与えることで、その本能を刺激できます。
まずはコオロギやデュビアなどの活きた昆虫を試してみましょう。
これらがうまくいかない場合は、「ハニーワーム」が効果的な選択肢となります。
もし、レオパが活き餌を上手く捕まえられない場合は、コオロギの足を取り除いたり、ピンセットで口元まで運んであげたりすると食べやすくなります。
強制給餌
食欲不振が深刻な場合、最終手段として「強制給餌」があります。
流動食専用の注射器を使用し、流動食を口から直接与えます。
流動食は、人工フードを水で薄めたり、ハニーワームなどをすり潰して作ります。
ハニーワームとヨーグルトを混ぜ合わせると、タンパク質と油分のバランスが良く、栄養価の高い流動食になります。
ただし、強制給餌はレオパにストレスを与える可能性があるため、獣医師の指導のもと、慎重に行うことが大切です。
ベビーをお迎えしたときの給餌方法

レオパのベビーを新しい環境に迎え入れる際は、さらに慎重な対応が必要です。
環境の急激な変化はストレスの原因となるため、お迎え当日の給餌は避けましょう。
早くても翌日、2〜3日後に給餌を始めるのが安全です。
レオパが新しい環境に馴れるまでには時間がかかります。
最初はシェルターに引きこもることが多いですが、外に出てくるようになったら環境に慣れ始めた証拠です。
この時点で様子を見ながら餌を与え始めるのが適切なタイミングとなります。
ゆっくりと新しい生活に馴染ませることで、ストレスを最小限に抑え、健康的な成長を促すことができます。

レオパは夜行性なので最初は夜に給餌しましょう。
レオパードゲッコーを購入する際は、お店やブリーダーの方にこれまで与えていた餌の種類と分量を必ず確認しましょう。
環境が変わっても、同じ餌を与えることで食べてくれる可能性が高くなります。
もし人工フードでの飼育を考えている場合は、お迎え時から人工フードに切り替えるのも良いタイミングです。
急激なフードの変更はストレスを与えることがあるため、最初は少量を混ぜて与えながら、徐々に切り替えていくことをおすすめします。

最後に…
レオパードゲッコーは、食事に関してはかなり気まぐれな面があります。
普段食べている餌を突然拒否したり、逆に頻繁に欲しがったりすることがあるのです。
しかし、レオパは絶食に対して強い耐性を持っているので、一時的な拒食は過度に心配する必要はありません。
アダルトであれば、週1回の給餌で十分ですが、普通に10日以上食べないこともあります。
また、長期間見向きもしなかった餌を突然食べ始めることもあるのです。
「レオパは気まぐれな生き物」と理解し、柔軟に対応することが、飼育のコツと言えるでしょう。

ぼくたちは気まぐれな生き物なんだよ。。

食欲がないときもあるけどあまり気にしないでね。
最後までお読みいただきありがとうございました🎵
レオパの飼育を始めてみよう!
レオパードゲッコーは爬虫類の中でも比較的カラダが丈夫で、初期費用、ランニングコストの面でも初心者には最適なペットです。
成体になると給餌は一週間に一回、寿命は10~15年と長い間生活を共にできます。
レオパは飼育環境への適応能力も高く、適正な温度と湿度を守っていれば普段あまり家にいない方でも簡単に飼育することができます。(もちろん飼い主としての責任とモラルは必要です)
⇩⇩こちらを準備したら、あとはレオパちゃんをお迎えするだけです!















